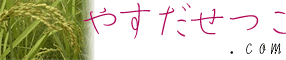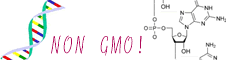農家の自家増殖禁ずる種苗法改定
はじめに
2020年11月12日から、国会で種苗法改定の審議に入るとのこと。その重大さをお伝えするために、以下の記事をウェブ上に緊急公開いたします。
全国商工新聞2020年6月15日 より
農家の自家増殖を禁止する種苗法改定は、批判の高まりで今国会での審議は見送られ、次期国会に持ち越されました。
種苗法は、新品種(登録品種)の育成者の知的財産権を守るための法律です。品種登録して育成車検を取得すると、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売などを一定期間独占できます。
登録品種は育成者権者の許諾を得なければ利用することはできません。ただし、農家が自分の農地で再生産するための自家増殖は例外として認められ、育成者の権利は及ばなかったのです。
自家採取禁止を目的とする改定案
ところが改定案は、これを180度転換し、農家の自家採取を禁止としたのです。農家は育成者権者に許諾料を支払って許諾を毎年得るか、許諾が得られなければ毎年すべての苗を購入しなければならなくなります。
さらに収穫物や加工品の売り上げにも対価が求められる可能性があります。侵害したと判定されると、10年以下の懲役または一千万円以下の罰金とする重罰が法案に盛り込まれました。
これまでにシャインマスカットはサクランボ、イチゴなどの優良品種が海外流出して問題になっており、これを防止するのが改定の目的とされています。しかし、農家の自家増殖を禁止するれば海外流出が防げるのでしょうか。
何より農水省自身がホームページで「種苗などの国外への持ち出しを物理的に防止することは困難」であるとし、「海外において品種登録を行うことが唯一の対策」と記載しています。
育成者権は、国ごとに取得する必要があり、品種登録していない国では育成者権は主張できないからです。
海外流出防止というのは後付けで、本当の狙いは多国籍種子企業のために農家の種取の権利を剥奪することにあると思われます。
「種子法廃止」「農業競争力強化支援法」からのトドメ
日米貿易交渉の下、規制改革推進会議を窓口として米国の多国籍企業のために日本の「岩盤規制」が次々と撤廃されています。これまでに「種子法廃止」で日本のコメ、麦、大豆の公的種子事業をやめさせ、「農業競争力強化支援法」で農業試験場が持つコメなどの遺伝子資源(種苗)や育成技術を企業に移転させ、そして、とどめが農家の自家増殖禁止なのです。これで公的種子や農家の手にある種子を、企業の種子に全て置き換えることができるのです。
今後、多国籍種子企業が日本で品種登録し、高額な許諾料を設定する事態が頻発しかねません。それは農家の大きな負担になり、日本農業衰退に拍車がかかります。
多国籍種子企業は、現在ゲノム編集種子に力を入れています。日本は規制なしの流通を認めたのですが、彼らが日本に乗り込んで高い利益を得るのに、ネックなのが農家の自家増殖容認です。
彼らの自家増殖禁止の要求が、今回の種苗法改定の背景にあるのかもしれません。
「9割は今まで通り」というが、それは今だけ
農水省は、登録品種は10%ほどで、90%は一般品種で今まで通り自由に種取りできると説明しますが、企業が主体になれば登録品種が増大することは必至です。
また、野菜類は8割が種取りできないF1種で、毎年農家は購入せざるを得ない種子なのです。
特に心配なのはコメなど穀物なのです。欧米では、主要穀物は農家の自家増殖を認めています。日本のように穀物までも企業に明け渡し、一律に自家増殖を禁止するような国はありません。
気候変動やコロナ禍による食糧輸出制限が起きる世界において、多国籍種子企業の限られた品種に依存するのは食糧安全保障をあきらめることなのです。
種を握るものが食糧生産を左右し、農家の手に種がなければ、国家の独立も危うくなるのです。種苗法改定は廃案にしなければなりません。
(2020/11/11)